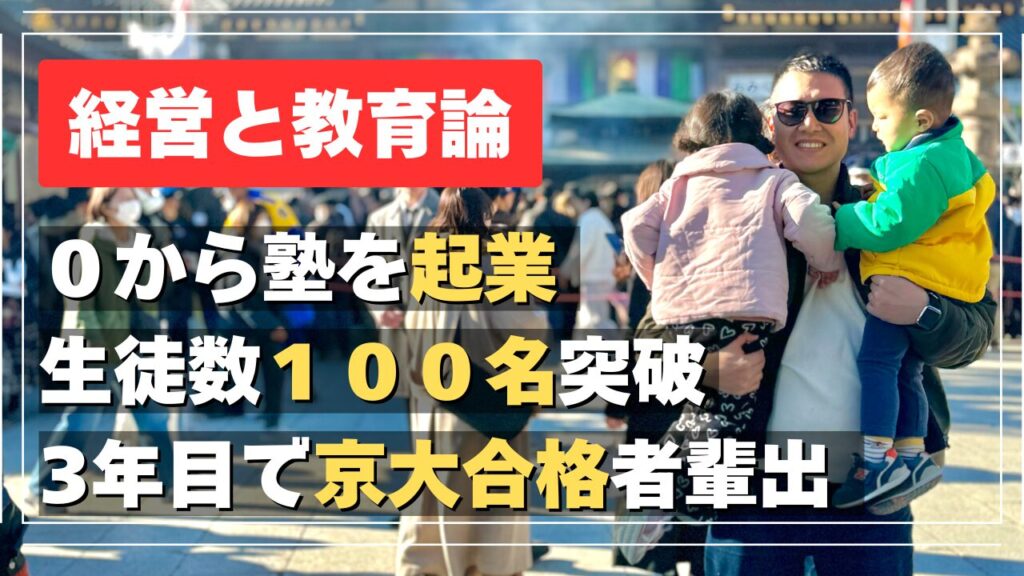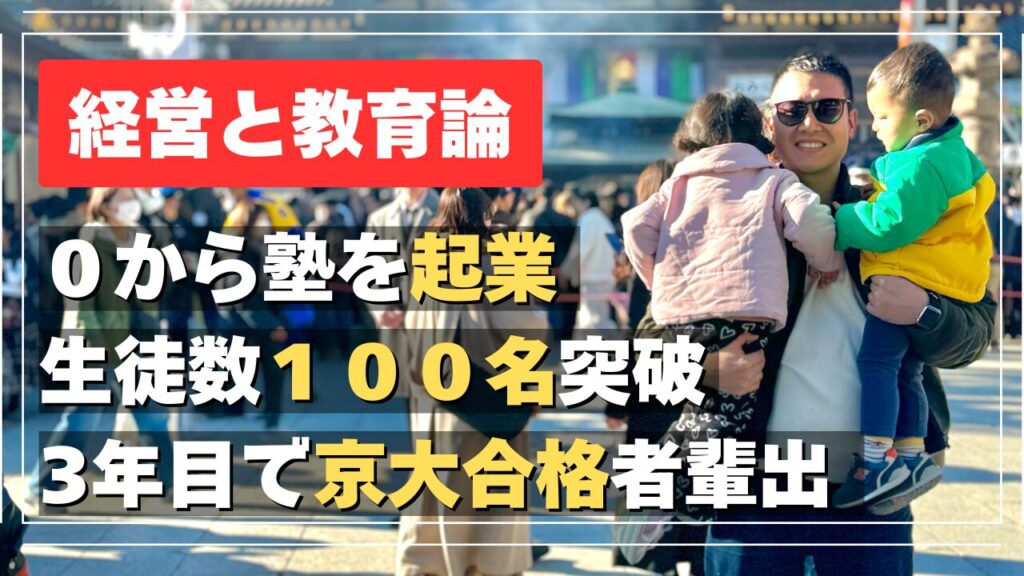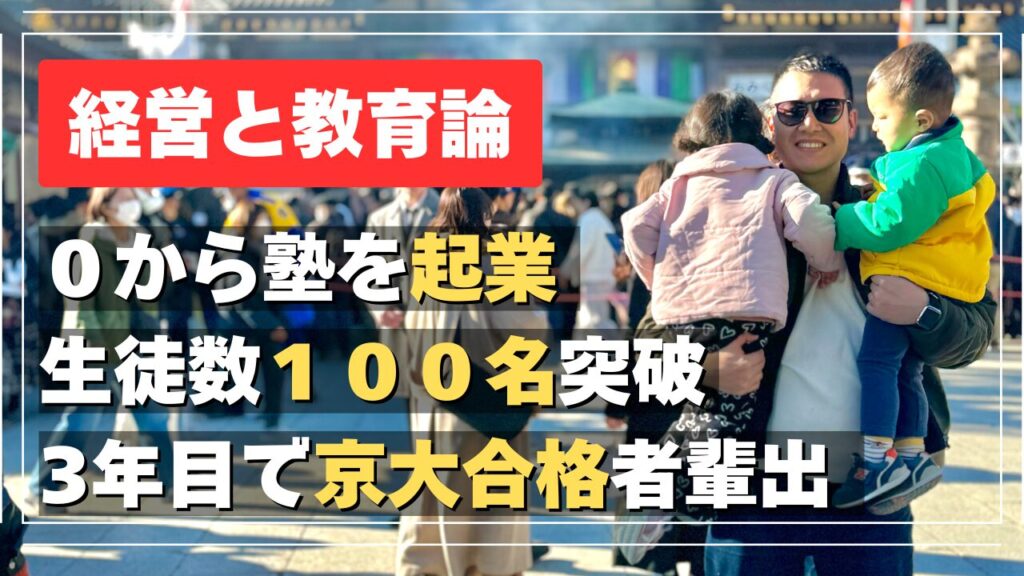ある保護者の方と2回目の面談を行いました。
今回の面談のテーマは、
『子どもに“勉強しなさい”と言わない取り組みをしてみませんか?』というご提案。
最初は「うーん、それはなかなか難しいですね……」と、正直とても悩まれていました。
でも最後には、『苦しいけど、やってみます』そう言ってくださったんです。
━━━━━━━━━━━━━━━
行動を強制することの限界
━━━━━━━━━━━━━━━
「勉強しなさい」という言葉は、確かに一時的に机に向かわせることはできます。
でも、その行動は“自分の意思”ではなく“親にやらされているもの”。
脳科学では、こうした「外発的動機づけ」による行動は、継続性が低いことが明らかになっています。
たとえば、有名なエドワード・デシとリチャード・ライアンの自己決定理論では、人がやる気をもって取り組むには「自律性」「有能感」「関係性」の3つが必要だとされていて、「やらされる勉強」はこのどれも満たさない。
だからこそ、「勉強しなさい」と言えば言うほど、子どもは勉強を“嫌なもの”として認識してしまうんです。
━━━━━━━━━━━━━━━
結果ではなく、過程を褒める
━━━━━━━━━━━━━━━
今回の面談では、「結果ではなく過程を評価する声かけ」についてもお話ししました。
これも科学的に効果が実証されています。
たとえば、スタンフォード大学のキャロル・ドゥエック教授による研究では、『結果(=能力)』ではなく『努力や工夫(=過程)』を褒められた子どもは、失敗を恐れずに挑戦し続ける「成長マインドセット」を育むことができるとされています。
つまり、「頑張ってるね」「工夫したね」「自分でやろうとして偉いね」という声かけが、その子の将来の『自己効力感』や『挑戦力』を育てていく。
━━━━━━━━━━━━━━━
“やらされる勉強”から“やりたい勉強”へ
━━━━━━━━━━━━━━━
子どもが本当に力を伸ばすのは、「やらなきゃいけない」から「やってみようかな」に変わった瞬間。
そのためには、強制するのではなく、対話をして、選ばせてあげること。
そして、やったことに対して、あたたかいフィードバックを届けること。
そうやって、少しずつ“自分でやる意味”を見つけていく。
そのプロセスを、一緒に支えていくのが僕たち大人の役割だと思っています。
━━━━━━━━━━━━━━━
次はいよいよ、生徒本人の番
━━━━━━━━━━━━━━━
保護者の方が「よし、やってみよう」と言ってくれた時、本当に嬉しかった。
ここからは、いよいよ生徒本人が変わっていく番。
僕たちも全力でサポートしながら、寄り添っていきます。
“勉強しなさい”を封印するのは簡単ではないかもしれません。
でも、その小さな変化が、やがて大きな自立へとつながっていきます。
今日もまた、一つのご家庭と一緒に、小さな一歩を踏み出せたことに感謝しながら、僕たちは子どもたちと向き合い続けます。
=======================
“パパ専門”子育てコンサル始めました!
公式LINEでお申し込み受付中です!
・子供との関わり方がわからない
・子供との関係性がうまくいかない
・未就学教育の方法がわからない
などなど
なんでもお問合せください!
まずは無料セッションから!
公式LINEはこちら↓
https://lin.ee/XRGyEr6
=======================
大学受験科:https://niischool.com
高校受験科:https://koukoujuken.niischool.com
個別指導:https://niischool-kobetsu.studio.site
=======================
代表の武末が教育に関することや日々代表として考えていることなど、毎日ブログとラジオを更新しております。
お時間ございましたら、ぜひご覧ください。
ブログ:https://note.com/yuta_takematsu
【生徒・教え子向け】
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8VccY2T-QeMazAaMCUEt7ad6w4xKKxf_
【保護者向け】
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8VccY2T-QeM-KzX4YA1G5NXScBMCPY6Y
=======================